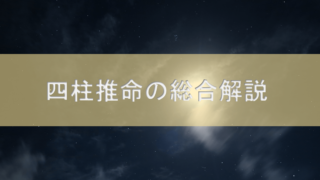今回は四柱推命の大運(たいうん)についてご説明したいと思います。算命学を学んでいる方にとっても参考にできると思います。
・大運について学びたい人
・大運と命式について知りたい人
・大運と年運について知りたい人
四柱推命の大運(たいうん)とは?
四柱推命で大運(たいうん、だいうん)とは、10年毎などのまとまった運勢を表す、人生で絶大な影響力をもつ運命です。
命式と行運(大運、年運(歳運)等)をあわせてみる際に、特徴的な五行の傾向をよむことができれば、該当年(月・日)の流れがわかります。
大運の流れの中で今はどの大運干支なのか、特定することは、はじめは難しいため、干支の学習を始めて、大運の切り替わりがくる直前まで追って捉えられればベストですが、
該当する大運は、流派によっては一個まるまる干支が異なることもあり、自分が今どの大運干支なのか判断することは初学者にとって難しいため、大まかにでいいので、自分自身の家庭・親との関係・仕事の状況、金銭面などを考えて、おそらくどの大運かということを予測するといいでしょう。
また、大運には十二支の季節毎に区切られる、いわば接木期という節目が30年毎にめぐる(10年遷移の場合)ことが知られていますが、この接木期は人生が大きく変わる時期であり、的中率が高いことは押さえておきましょう。
下記は大運のポイントです。
・大運支に通根する天干に重きをおく(力量が大きくなる)
・命式と大運を推命する
・大運と年運を同時に判断する
・大運支との合、沖の有無を把握する
・約3年前から大運干支が切り替わり始まる
大運支に通根する天干に重きをおく(力量が大きくなる)
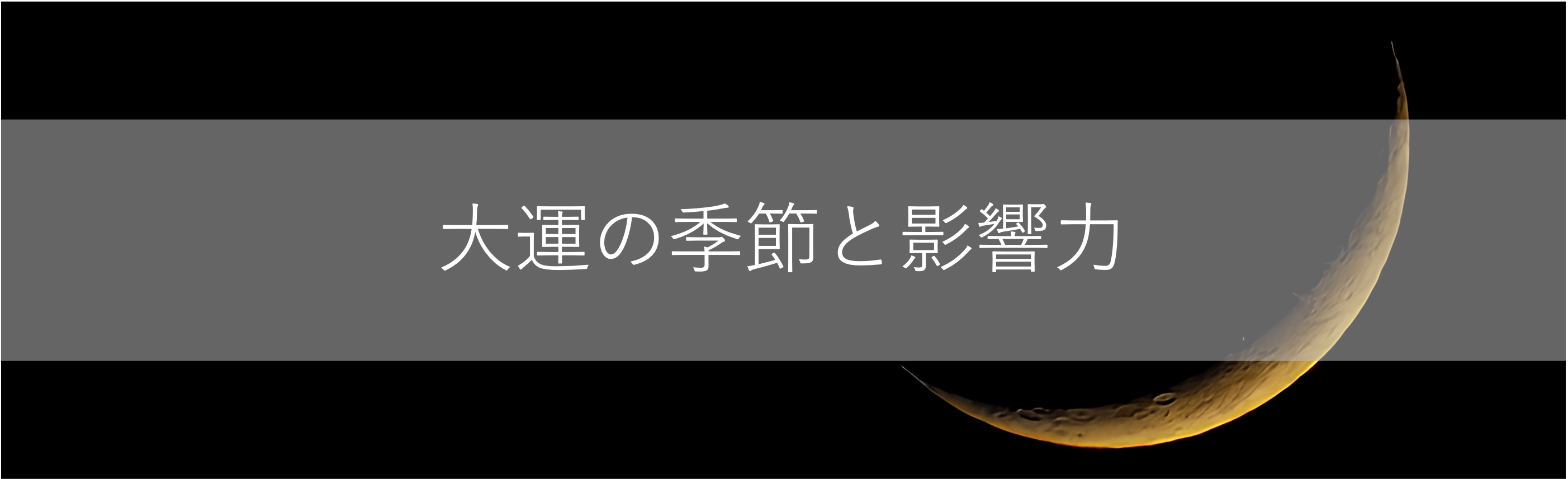
四柱推命を学習する上で大切で奥深いものが、大運(たいうん、だいうん)。
この運命を判断に入れ、巡る現象の的中率を上げることができれば、大きな人生の流れがわかります。
大運の干支と歳運(年運)の干支は、とても影響力があり、月支より重きをおいて推命しましょう。
日月年 大運
辛戊癸 戊己庚辛壬癸甲乙丙丁
丑午卯 午未申酉戌亥子丑寅卯
夏→秋→冬→春
例えば、上記のような命式では、大運支は夏、秋、冬、春へと季節が移り替わります。
もちろん、大運が夏なのに、歳運(1年運:年運)で、四旺の十二支(卯午酉子)がめぐることにより、季節が一年ごとに変わる(三合半会等により強弱が出る)ことがあるため、大運だけでなく、歳運や命式を同時に判断することが大切です。
そして、季節は十二支から読み取ることができるので、その季節が象徴する通変星が意味する環境が大運という運命からわかります。
一方、大運干支の天干をみると、その10年等のまとまった期間の流れを読み取ることができます。
強まる通変星による象意(※1年毎)
※天干のどの通変星が強いのか、歳運などの行運をまとめて考慮し、どの五行に偏り、結果的にどの通変星が強まるのか、時々の運命により、象徴される意味合いが毎年変わると考えていいでしょう。
命式と大運・歳運を推命する

命式を大運支を交えて推命する方法は、流派により異なることが少なくありません。
ここでは、大運支に通根する天干の作用が強くなることを前提に話を進めていきます。
日月年 大歳
辛戊癸 甲癸
丑午卯 子卯
命式内の日干辛を育てるに当たって、大運支がいいかどうかをみていくことが大切です。
大運支、月支に通根する天干が、強い力を得る天干であることも押さえましょう。
大運支に支えられている年干と歳運の天干の癸が強まっているため、この年は特に、癸の影響力が強い1年になることが考えられます。同時に、相生の関係で甲が強まっていることもポイントです。※干合により、癸から生じた強い丁が潜在しています。
このように、大運支子にしっかりと通根するかどうかという天干の力量を考えることが大切になります。
総じてみて、命式にとって必要な五行と不必要な五行の傾向がわかれば、時期的な運勢の判断がつきやすくなります。
つまり、行運の60干支と全体的な五行の偏りの傾向や五行の強まりやすい流れが一度わかれば、時期的運勢は予想しやすくなり、的中率は上がります。
身旺で活躍期に該当する時期(適度な身旺で財星が巡る)や、身弱で責任に押しつぶされる時期(身弱で官星がめぐる)など、身旺・身弱によっても意味合いが変わることがあります。
大運と年運を同時に判断する
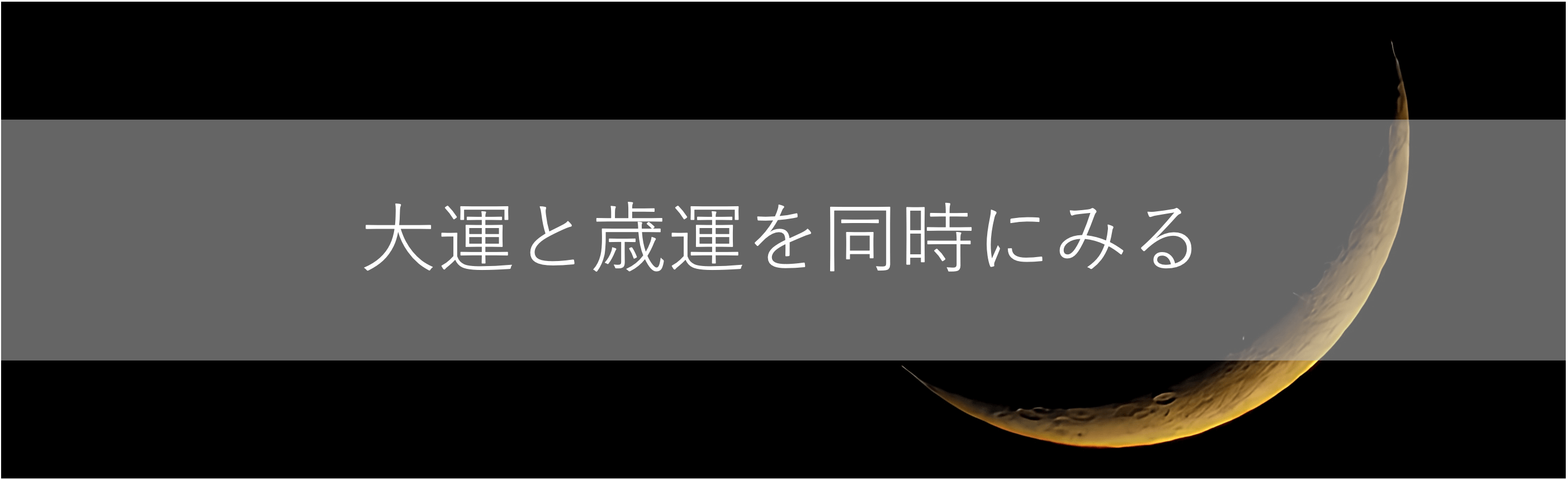
大運干支と年運干支、命式の3者を総合的にみることがポイントです。
日月年 大運 年運
辛癸庚 丙 辛
丑酉子 子 丑
大運干支丙子と年運干支辛丑がめぐる場合、どのような時期になるのでしょうか。
大きな視点をもつと、大運支は子であり、日干辛は真冬の時期にいます。また、年運支の丑は1月です。
つまり、冬の季節の中に日干辛は存在し、辛にとってどのような状況が想定されるのか推命することになります。
大運支との合、沖の有無を把握する
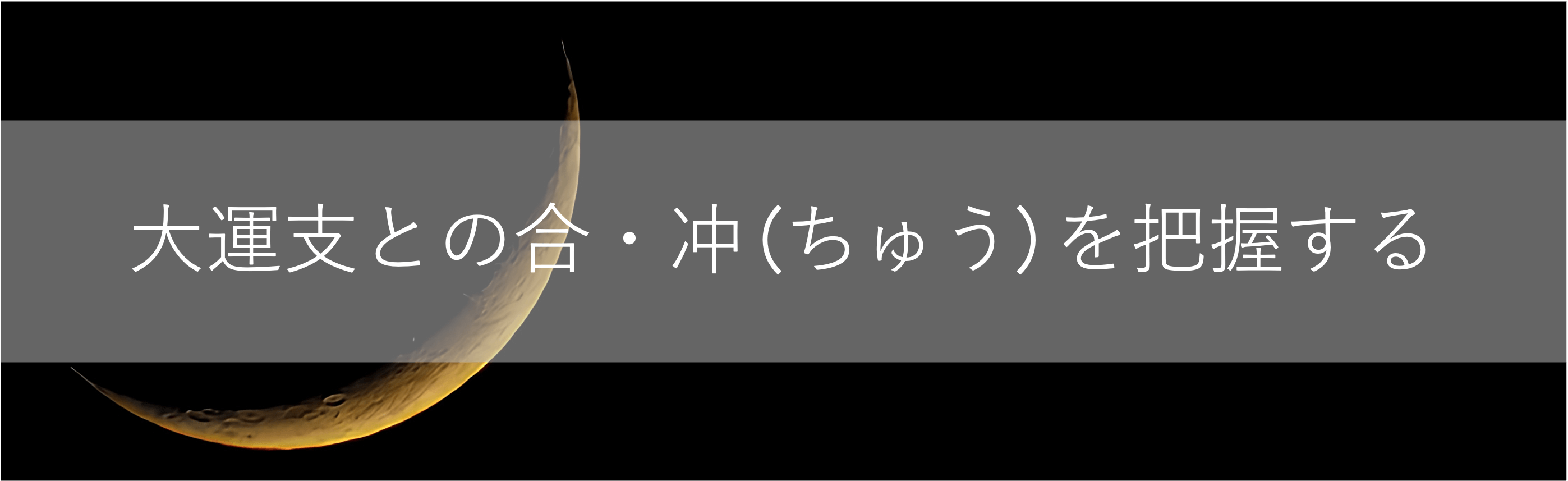
次に、命式内の干支と運命(大運、年運)との干合(かんごう)、三合(さんごう)、方合(ほうごう)、支合(しごう)、沖(ちゅう)があるかをみます。
日月年 大運 年運
辛癸庚 丙 辛
丑酉子 子 丑
優先順位は流派により異なることが少なくないですが、概ね大運支・月支・日支・歳運支・年支は重視されます。このことを考慮にいれ、大運支と日支が支合、月支と年運(歳運)の十二支が三合半会して生じる五行が日干辛にとって吉と出るか凶と出るか推命します。しかし、三合はポジティブな現象が起きることが多いため、あまり悲観しすぎる必要はないでしょう。
三合などが複雑に絡まり、どの合や沖を採用していいのかわからない場合、一度すべての作用を書き出し、優先する十二支に関連する合から生じる五行に重きを置くと上手く推命することができます。重きを置くのは大運支や歳運支等であり、これら干支との作用がみられた場合は、ほぼ確実に現実的にも影響がでます。
細かく推命したい場合、生じる五行の通変星が意味する事象が起きることを予想するのもいいでしょう。しかし、的中率を考えると、その人にオリジナルな干支の並びや干合・三合(半会※複数かかる)・冲(合・冲が入り混じる)の作用があればあるほど象徴的な出来事が起きる確率は高くなります。
したがって、苦手な干支や気の流れが良くなる干支の組み合わせを理解することが推命を円滑にさせ、的中率に影響します。一方、初めて占う人は手探りの状況で推命していくことになるため、的中率は下がるでしょう。
また、年代により各柱の重きを変化させて考える場合もあります。推命する時点での年齢によりどの柱に重きを置くかという視点で重視する十二支を変えることも面白いと言えます。
約3年前から大運干支が切り替わり始まる
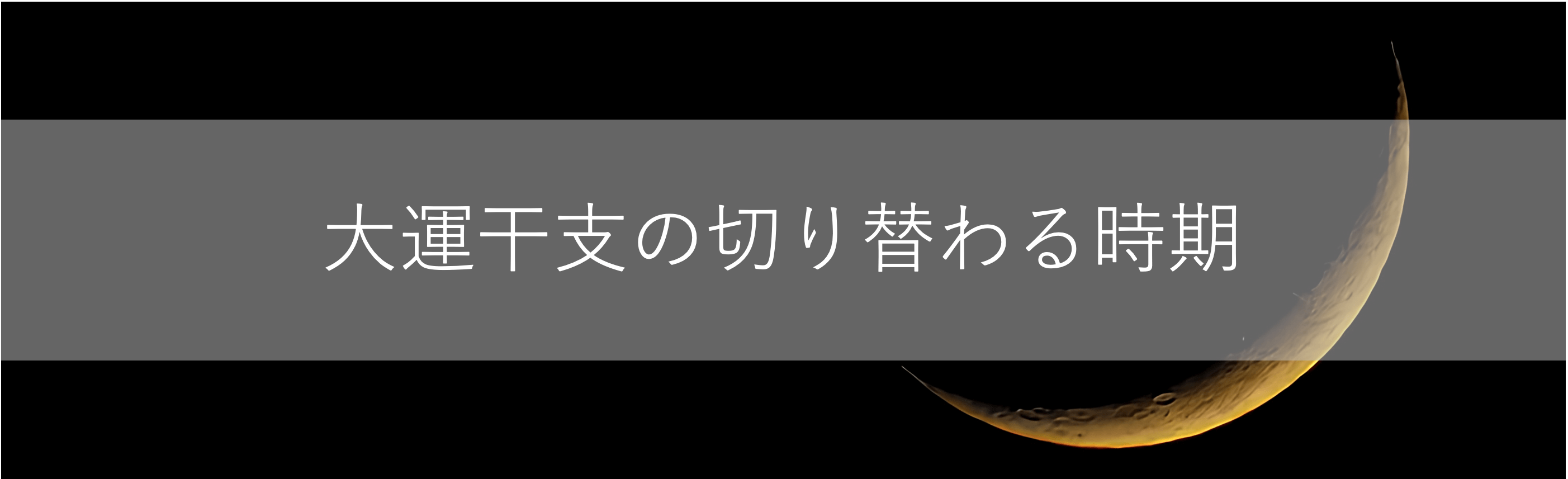
大運干支は10年毎に遷移する場合、その変わる始点はいつかという疑問があるものです。
大運干支が切り替わるおよそ2,3年~5年ほど前から徐々に次の大運に変わり始めることが分かります(今と次の大運干支の影響が混じるグレーゾーンが存在する可能性があります)。
また、大運は天干が前5年、十二支が後5年(蔵干分率次第ですが、辰であれば、乙が約1年半・癸が約6ヶ月・戊が約3年※10年遷移の場合)という説や分割せず10年すべてが大運干支などと諸説あります。
大運の切り替わりをはっきりと捉えることができれば、どの大運干支に自分自身がいるのかが机上ではなく明確にわかるようになるため、干支の学習者は、切り替わりの時期は注意して推命しましょう。